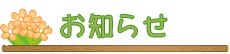ここネット通信 3月号
『ママがいい』と『3歳児神話の崩壊』
副会長 中川浩一
昨年12月にここネットのzoom研修会で松居和先生のお話しをお聞きしました。また著書「ママがいい」を読んで私も納得と感動した一人です。保護者が0・1・2歳のわが子としっかり関わり、可愛がることによって子どもは心が安定し、安心して育つことができます。さらに『子育て』という営みは、子どもが育つ以上に親が育つ、「親心」が育っていくという相互作用の営みであると。私自身心から納得です。
そもそも、なぜ子育てという営みによって「親心」が育つのでしょう?それは親として子どもを授かり産んだ瞬間から、自分の意思とは関係なく自分の時間は目の前の子どもに奪われ、自分のやりたいと思ったことが何もできなくなるという「不自由体験」をします。その体験を経験し乗り越えていく過程で「親心」が育まれるのです。
ところが、現代社会は、核家族化、少子化、地域コミュニティーの崩壊など、子どもが育つ環境がとても厳しくなりました。なぜなら、そもそも人間は一人では子育てができない動物なのです。父親、母親はもちろんですが、周りの大人の関わりや子ども同士の関わりがあって子どもは成長します。そのことを京都大学の明和政子先生は、共同養育・集団養育こそがホモサピエンスとしての生き残り戦略であり、本来の子どもの育て方であると。
「ママがいい」という不変の子どもの叫びに母親一人では応えられない社会状況になっているのです。
そして昨今の国の保育施策は、松居先生が言われるように母親の就労支援を目途に長時間保育、休日保育、病児保育、保育の無償化など、子どもを預けないと損、子どもを預けることはあたり前、親の権利であるといわんばかりの現状があります。このように母子分離が進む施策が次から次へと打ち出されてきました。これではなかなか「親心」を育むことは出来ません。このことに警鐘を鳴らされているのが『ママがいい』だと思っています。
だからこそ、この時代に親に代わって保育する保育所やこども園の使命は大きく、保育士の子どもに寄り添う日々の保育で子どもの育ちは支えられているのです。また孤独で子育てをする「ワンオペ育児」や「ぼっち子育て」によって育児疲れ、児童虐待につながるような保護者をも支えていると自負しています。
今年2月に開催された『第14回真冬に保育を考える研修会』で、東北大学の大田千晴先生のエコチル調査の分析から見えてきた『三歳児神話に根拠なし』というお話しがありました。松居先生のお話の真逆のような演題名でしたが、果たしてそうだったのでしょうか。乳児をお預かりしている私たちの肌感覚でいうと、友だちとの関わり方、困難を解決しようとする力など、いわゆる「社会性」や「レジリエンス」という発達に関しては、1歳、2歳で入所してくる子どもと比べてみて3歳時点で発達しているというデータは妙に納得できます。
だからといって私たちは、積極的に乳児保育を推奨していません。あくまでも就労や保護者の疾病などによって自分で保育が出来ない保育を必要としている保護者に代わって保育をしています。保育所やこども園を利用したいと思うときに「3歳児神話」に囚われ、自分で何が何でも育てなければと思われる保護者にとっては、保育を利用することへの後ろめたさがこの調査で少しでも軽減されるといいなと思っています。
同時に私たちは、これに慢ずる事なく、「ママがいい」はあたり前、親に代わることはできないけれど、子どもたちひとり一人にしっかり寄り添っていける保育者になろうと謙虚に受けとめ、さらに松居先生が言われる「親心」を育んでいくことのできる保育を目指していきたいと思います。保育園やこども園や子育て支援センターがどこまでできるかわかりませんが、親子の絆が深まるような日常・非日常の時間と空間を作りたいと思います。