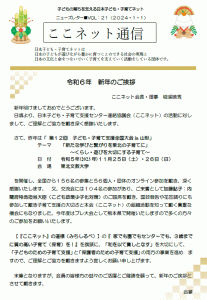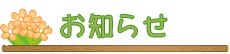ここネット通信 7月号
ここネット副会長 大谷光代
【くまっしぇ】より
埼玉県熊谷市はかつて暑さ日本一の町として有名になりましたが、支援拠点活動も熱く盛り上がっています。以前もここネットで紹介させていただく機会がありましたが、熊谷市の全支援拠点で構成された「くまっしぇ」の活動のひとコマを報告させてください。
つい先日の7月定例会でのことです。議題討議が終了した後、ひろばの「予約制」についてつぶやきが出ました。
利用者さんに「熊谷はいつまで予約制を続けるの?元には戻らないのですか」と言われたとのこと。またそういう声は多いらしい、とのこと。
コロナの際、くまっしぇでは拠点の開所状況の足並みを揃えることにしました。市直営拠点もくまっしぇの一員だということもあり、コロナ禍下での事業について行政と相談の上、状況に応じてすんなりと方針を決め共有でき、次第に予約制にして人数制限を図っていく流れが自然とできていきました。また、たまたまコロナ突入の前年に作った「くまっしぇ育自ポータルサイト」で、親さんたちがいつでも各拠点の予約状況の確認ができるようにもなり現在に至ります。
コロナが5類になってから一年が経ちました。今でもくまっしぇに予約制は残っていますが、予約制をとるのか否かはあくまで各拠点の判断です。5類移行以前から予約なしで受け入れを頑張っていた拠点も複数あり、前述の質問はそちらをよく利用する親さんからいただいたご意見でした。
県内でも予約制で受け入れているところは少数になってきていると聞きます。ということは全国的な流れなのでしょうが、親さんの意見に合わせ予約という考えは排除すべきなのでしょうか。
くまっしぇの中で予約制を続けている拠点の中には、コロナを通して自分たちの支援の仕方が変わった、と言うところもあります。それまで、家で一人子育てしているなんてとんでもない!全ての子育て親子さんを拠点利用者にしなければ!という盲目的ながむしゃらさで利用を促していた、ということにふと気づいたとのことでした。人数制限のかかったゆったりした拠点を眺めながら、その人それぞれのやり方を尊重すればいいという気持ちに切り替わったそうです。コロナがきっかけで「がむしゃら型支援」から「よりそい型支援」へ移行し、今のまま予約制の人数制限をしながら親子さんの横で寄り添いたい、ということです。
定例会の最後、幅広くアンケートを取ってみようということになりました。予約制なしでいつでもどこでも利用できる方法を切望する方もいるでしょう、予約制の中で安心してゆったり利用したい方もいるでしょう。その集計後、私たちが何を感じ
何を考え、どんな方法を選択していくのか。また皆様に聞いていただけましたら嬉しく思います。
これから夏本番。暑くても、親子さんが遊び集う場として支援拠点が必要とされていくことと思いますが、皆様ご自身もお身体ご自愛ください。