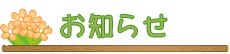ここネット通信 2月号
第14回真冬に保育を考える研修会報告
副会長 中川浩一
去る2月10日・11日に毎年開催している「真冬に保育を考える研修会」を山口県下関市で開催しました。県の内外75名の方が参加、日本列島が冷蔵庫の中に入ったような寒い中でしたが学びが深く、かつ多い研修会となりました。
まず研修1では、令和8年度から正式事業となる「こども誰でも通園制度」について今年度試行実施している北九州市の北野久美先生にお話しをして頂きました。注目すべきは、「こども誰でも通園制度」の話しを聞いたとき正直「無理!」と思ったけれども、やってみて今はこれって「有寄りの有」という結論に至ったというお話しでした。
研修2では、東北大学大学院教授で大学病院の小児科医をされている大田千晴先生から「エコチル(エコロジーとチルドレン)調査」のお話しを聞きました。早期保育を受けた子どもと家庭で育った子どもが3歳なった時点でどのような「発達」の違いがあるのかという4万人の膨大なデータ分析を元に『3歳児神話に根拠無し』というお話しは、乳児保育を後ろ髪を引かれる思いで利用している保護者や子どもへの後ろめたさから、利用控えしている保護者、さらに保育者の私たちにとっても、大きな後押しになるお話しでした。そして日本でも根付いている「エコチル調査」という大型縦断調査の分析から見えてきた保護者の喫煙による子どもの受動喫煙やスクーリング時間(メディアとの関わる時間)の長短など、子どもが育つ環境が子どもの育ちへ及ぼす影響についてのお話しはとても興味深いものでした。
そして研修3では、ここネットのスーパーバイザー的な存在でもある武庫川女子大学教授の倉石哲也先生からは、保護者を虐待の加害者にさせないための保護者支援の方法について具体的かつ多岐にわたる方法を教えて頂きました。
そして研修4では、至誠館大学教授の田中浩二先生からは、リスクマネジメントを通して『ケガは仕方がない』と安易に思ってはダメ、死亡事故を0にするためには、まず重大事故を起こさないという保育が大事である。そのためには小さな事故やトラブルが起きた時に保育者が何故起きたのか、どのようにすれば起きなかっただろうかという「考える保育」の重要性をデータの分析を元に教えて頂きました。
それぞれ「角度は違いますが、どの研修も今の時に適った保育の視点を大いに学び合えたのではないかと思います。このたびの「第14回真冬に保育を考える研修会」にここネットを通じて全国から、そして県内からお集まり頂き熱い議論と学びができたこと、この場をお借りして御礼申し上げます。
ありがとうございました。